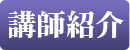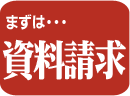本を読むということ
どの学年も、国語の力をつけることに頭を悩ませているようだ。そして、その解決方法として「読書」を挙げる人が多い。一方で読書は、各教科の成績アップのためにもいいと考えている人が多い。朝の「読書の時間」などがそうだ。
しかし、本当に「読書」は万能なのだろうか。
まず、「学ぶ」ことを前提に読書するなら、「文学書」でなくてはならない。ベストセラーに代表される「娯楽小説」では、言葉や漢字あるいは表現方法などの勉強にはなりにくいと思うからである。しかし文学は、多くの若者にとって「おもしろくない」本であろう。往々にして文学書は、ストーリー自体は興味を引くものではない。なにしろ、文学書は「おもしろい」ことを目指して書かれたものではないからだ。文学書は作家の主義や主張(この時点で、中学生は尻込みする)、日本語の美しい表現などを追及したものである。姜尚中氏が夏目漱石を崇拝し「こころ」を執筆したのも、夏目作品の言葉の美しさからであるという。それを中学生が読むか?
次に、文学書を読んだからといって、国語力がつくか。私は、大学時代から数えると、おそらく3000冊近くの本を読んだ。しかし、そのことで国語力がついたとは全く思えない。本を読むことが好きだから読んだだけで、国語力をつけたいと思って読んだわけではないからだろう。
すると、勉強のために読書すると読書がつまらなくなり、好きだから読書すると国語力がつきにくい。まさに、八方ふさがりである。
また、読書すると学業成績が上がるというが、それは本当だろうか。東京大学(あるいは旧制一高)出身の作家も数多くいるだろうが、そうでない作家もいる。たとえば作家の坂口安吾は、小学校だか中学校だかを退学している。学校を去る時に、机に「余は偉大なる落伍者となって、歴史の中に甦るであろう」と、彫刻刀で彫ったという。そんな坂口安吾の本も「堕落論」をはじめとする秀作をあまた残している。読書量と学業成績は、本当に一致するのか?
私は、読書する人が成績が上がったのではなく、成績がいい人が読書をするものだと思っている。なぜなら、読書をするためには、それを理解するための最低限の知識や能力(これを言語リテラシーとも言うらしい)が必要だからだ。
私は、初めて本らしいものを読んだのは大学生になってからだ。それまでは、夏休みの読書感想文も、巻末の「解説」などを丸写しして提出いた。読書など面白くもなんともなかった。大学受験のとき、夏目漱石の「門」が問題として取り上げられた。それを読むうちに、もっと続きを読んでみたいと思った。そして大学入学後に読んだ。それが私の読書の始まりである。
本は面白い。考えさせられるし、知らないことを教えてくれる。自分の愚かさや無知を思い知らされるとともに、また頑張ろうとも思わせてくれる。本は面白い。ただ「面白い」という理由だけで本を読む。それでいいではないか。