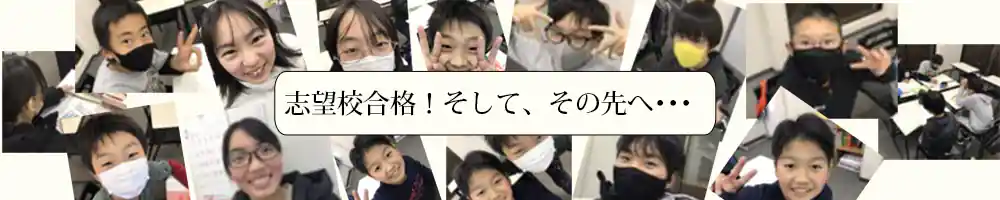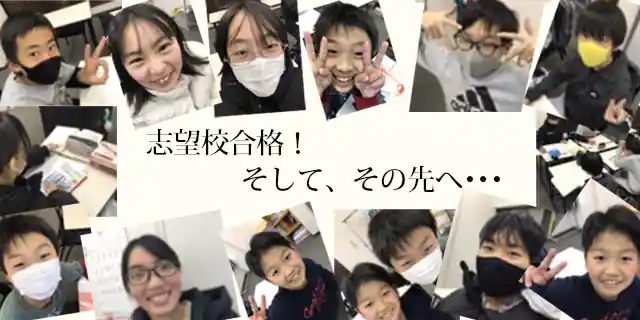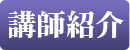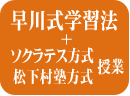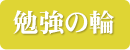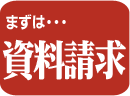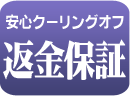答えにたどり着くまで
小学校から高校までの勉強とは、新しいことを学び修得することであろう。新しいことに取り組み続けるのだから、その問題を解いて、間違うことも少なくないはずだ。
大切なことは、正誤よりも、「自分は、どんな考え方をしたか」であり、間違っていた時も「なぜ、自分の回答が間違っているのか」「なぜ、その正答になるのか」である。
ところが多くの生徒は、「正しい答えは何か」ばかり追求する。正しい答えに至る考え方や正しい答えに必要な知識などには、ほとんど関心を持たない。
だから例えば数学など、
生徒「問2の答えは2です。」
講師「いいえ、違います。」
生徒「じゃ、-2です。」
となる。
この「じゃ」とは何なのか。「2」でなければ「-2」だ。この姿勢を「勉強している」というのか。答えが「2」になる考え方が間違っていたなら、その考え方のどこに誤りがあったのかを考えなければならない。さらに正答が「-2」なら、なぜその答えになるのかを考えなければならない。
自分が導き出した答えが合っていても間違っていても、どうでもいいではないか。間違うことで学ぶことがあるなら(むしろ、間違うからこそ学べることが多いのだが)、間違うことは決して悪いことではない。自分の答えが合っていたとしても、「教えられたとおりに解いたら、それが正答だった」というのでは、何も身につかない。
また、答えにたどりつくまでの道のり(思考過程)は、ひとつとは限らない。
例えば「三角形の合同」を証明する場合でも、「2辺とその間の角がそれぞれ等しい」で解いた生徒もいれば、「1辺とその両端の角がそれぞれ等しい」で解いた生徒もいるかもしれない。そしてそのどちらの解法も論理的に正しいのかもしれない。正答がひとつでも、思考過程・論理展開がひとつだとは限らないのである。
最初に発表し正答した生徒の解法と自分の解法が違っていても、直ちに自分が間違っていると判断せずに、自分の解法が正しかったのかどうかを確認しなければならない。
小中学生の学習は、黙って進めてはならない。ただ座って話を聞いているだけではなく、しゃべって、書いて、失敗を恐れず進めなければならない。よく「わからないところがわからない」というが、それ以上しゃべることができなくなったとき、それ以上書くことができなくなったとき、そこがわからない場所だ。
わからないところがわかれば、あとは「やるだけ」だ。
そう。間違いを恐れず、しゃべって考え、書いて考え、考えてしゃべり、考えて書く。それが勉強だ。
これに尽きる。