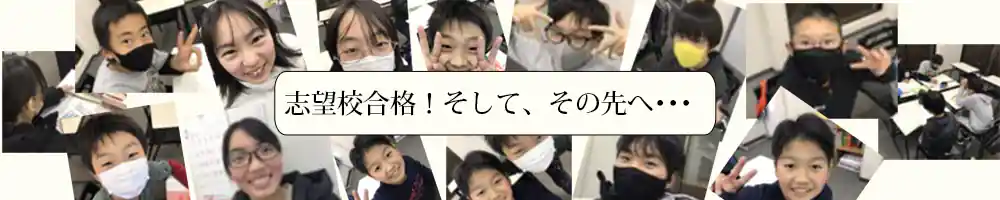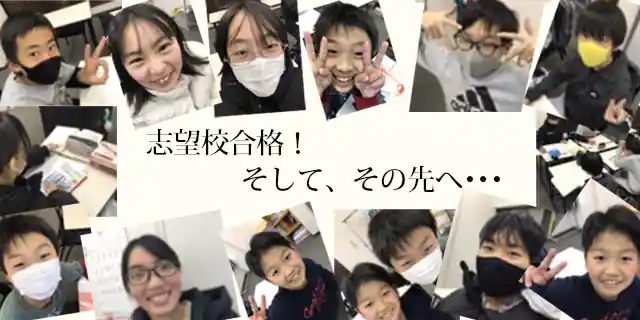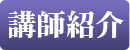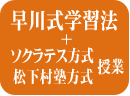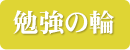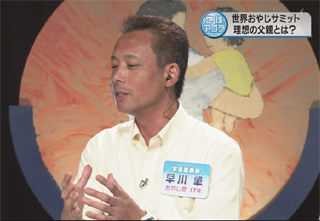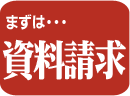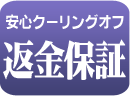2026年2月 5日
それにしても、野党がだらしない。
スローガンばかりで、具体性がない。反対ばかりで、代案がない。
例えば憲法改正で、「時代にそぐわない憲法を変えよう」と与党は言う。
しかし日本国憲法は、時代に合わせて変えていくものなのか?
明治維新から太平洋戦争終結まで、数えきれないほどの命が犠牲になった。そうして手に入れた「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義」の理念は、時代に合わせて変えていくものか?
むしろ、日本国憲法に合わせた時代を作るべきではないのか?
強い日本を作るとも言う。強い国とはどんな国だ?戦争に負けない国か?そんな国があるのか?
そもそも、たくさんの自国民と相手国の命を奪う戦争に勝者はあるのか?
強大な武力を背景にして、つべこべと屁理屈を並べて石油やレアアースが眠る国を侵略する国は強い国か。
そしてその「強い国」をつくるために、戦闘機や戦車や軍艦をつくる。そのための費用は税金から捻出される。「五公五民(収入の50%が租税公課、手取りは50%)」と言われる現在、さらに税金を上げてもいいのか?
これからも労働者人口・納税者人口は今後も減り続けるから、税の負担額はさらに上がる。
平和ボケ、いいじゃないか。世界中が平和ボケになればいい。
緊張した社会の、何がうらやましい?
公共の福祉に反しない限り(=他の人の人権を侵さない限り)、私たちは何でもできる。
何を考えてもいい、何を言ってもいい、何をしてもいい。どこに住もうが、どんな仕事をしようが、それは自由だ。
そんな日本を、なぜ変えようとする?
2025年12月 3日
街灯の下で鍵をさがす人
経済学で使われるらしいが、こんな話がある。
ある夜、公園の街灯の下で、何かを探している人がいる。
そこを通りがかった人が、「何を探しているんですか?」と訊くと、「鍵を失くしたんです。」と答える。
「どのあたりで失くしたんですか?」と訊くと、こう答えた。「向こうの暗いほうです。でも暗くて探しにくいんで、明るい街灯の下を探しています。」
この話は、私が「勉強とは何か」という話をするときに、引用するひとつだ。
例えば受験勉強は、ある一定期間で、希望する高校に合格する学力を身につけなければならない。その学力は、「覚えること」「理解すること」「解くこと」を繰り返し続けることで身につく。
でも大抵の中学生(私もそのひとりだったが)は、英単語や熟語、漢字やことば、世界史や日本史の出来事などを覚えることが苦手だ。というか、苦痛だ。しかも(例えば歴史分野などは)機械的に覚えるだけでは忘れてしまう。覚えても覚えても、すぐに忘れる。あるいは他の何かと混乱する。とても正確に覚えきれるものではない。だから、理解しながら覚えていかなければならない。理解するには質問したり、調べたり、とても手間がかかる。そして問題を解いても、覚えたはずのことや理解していたはずのことができなかったりする。
それでも続けなければならない。勉強とはそういうものだ。どれほど苦痛でも、それをしなければ学問が身につかないなら、決して避けてはならない。暗い闇の中を手探りで、君は君の勉強方法を探し続けなければならない。誰にも当てはまる勉強方法などない。君の勉強方法は、君だけのものだ。そしてその勉強方法は、君以外の誰にもみつけられない。だから誰かが君に、君の勉強方法を教えることもできない。
明るい場所を、誰かと何年かけて探そうが、そこには鍵はない。
2025年10月22日
ひとは、死んだらどうなるのか?
「ひとは、死んだらどうなるのか」「ひとは、何のために生きるのか」。小学校高学年から、遅くても中学生2年生くらいまでには、「生きるということ」「死ぬということ」についての疑問を持つ。
ひとは、死んだらどうなるのか。どうにもならないし、何にもならない。命が消える、ただそれだけだと思う。
「命」とは、何かの形として存在するのではなく、身体に宿る「生きる力」である。「死ぬ」とは「命を失うこと」つまり「生きる力が消えること」である。
命は、ある意味では、「炎」に似ている。
何かに火を点けると、それは熱と光を放つ炎になる。炎は風が吹けば消えるし、そのままにしておいても、いつかは消える。消えた火は、その形を何かに変えたわけではなく、どこか別の場所に移動したわけでもない。ただ消えただけだ。
ひとの死についても、消えた命が別の形に変わったわけでもなければ、どこか別の場所に移動したわけでもない。
点けられた火は何かの折に消えてしまうこともあるが、何もしなくても、ただ燃えているだけだ。
しかし、その光と熱を活かすこともできる。闇の中で不安でいる人や進むべき道に迷っている人に、光は安心を与えてくれ、行き先を照らしてくれる。寂しい人や心が寒くて震えている人に、火は暖かさをくれる。
命と炎が違う点と言えば、炎は燃えるものと空気さえあれば燃え続ける一方、ひとが生き続けるには理由が要る。いわゆる「生きがい」「目標」と言われるものだ。命=生きる力は、ひとの内部から自然に湧き上がってくるものではない。もしそうなら、何の悩みもなく充実して楽しい毎日を送っているはずだ。
生きる理由は、自分自身でつくらなければならない。「探す」のではない。「つくる」のだ。生きがいや目標がどこかにあるのなら、誰でもいつかは見つけることができるだろう。しかしそんなものは誰も用意してくれないし、どこかにあるわけでもない。
生きる理由は、自分でつくるしかない。
「ひとは、何のために生きるのか」これは、誰もが納得できる答えがあることが前提の質問だ。ひとが生きる理由がどこかにあると、なぜわかるのか。
生きる理由がどこにもないなら、自分でつくれ。何でもいい。「明日は、この服を着よう」でもいいし、「今週末は食べ放題に行こう」でもいい。
一生懸命に考えても生きる理由が見つからなければ、生きる理由なんかなくてもいいと思えばいい。火が光や暖かさを与えてくれるように、君の生きる力は、きっと誰かに光と温かさと笑顔をもたらしていると思う。
生きる理由なんかなくても、それだけで十分だ。それだけで、生きる価値がある。
僕は、そう思う。
2025年7月 3日
2025年度夏期講習
いよいよ光輝学院23回目の夏期講習が始まる。
今年の中学生は、これまで以上にヤル気まんまんだ。
例えば、いつもの夏の中3授業は朝9:00から始まる。ところが今年はなんと、「先生、7:00からにしましょう。」ときた。「先生はどうせ、早起きして、ウオーキングしているんでしょ? だったら起きられるでしょ。」と畳みかけてくる。
早起きするだけではない。早く始めるということは、午前中に3時限のところを4時限にできる。すると、午後も合わせて、1日に8時間の授業ができる。それを「毎日やってほしい」だと。
イヤだ、イヤだ。早起きするとかしないとかではない。
これまでの22回の夏期講習と冬期講習では、私の授業がない時間があるということを知ると(実際に講習が始まった後でも構わずに)、「先生、この時間に授業をしましょう」などと言って勝手に授業を増やされてきた。例えば、中3授業が86時限で始まった冬期講習が、終わったときには110時限の授業になっていた。それでも、朝9:00から授業をやれとは言われなかった。しかも、夏期講習では授業時間を増やす提案は(まだ)なかった。
夏期講習の段階で、とんでもない回数の授業を受けたがる今年の生徒だ。冬期講習には何を言い出すか知れたものではない。
それでも、6月に入ったら、今まで以上に健康を保とうとする自分がいる。
頑張れ、オレ。たくさんの授業を受けたいなど、講師冥利に尽きるではないか、イヤだけど。毎日毎日その日が終わると、一言もしゃべりたくないほど疲れるなど、望むところではないか、イヤだけど。教壇の上で倒れるなら本望ではないか、イヤだけど。
それでも、7月に入ったら、一人ひとりの授業方針を考える自分がいる。
あぁ、今年も夏が来た。
2025年6月24日
覚悟
6月21日付の朝刊コラムに、「日本の首相と米大統領がそろって靖国神社に参拝すれば、日米同盟の強固さと台湾海峡でともに血を流す覚悟を内外に示すことができ、何よりの抑止力になる」とあった。
前半はともかく、後半の「台湾海峡でともに血を流す覚悟を内外に示す」には異論がある。
私たち日本人は、台湾海峡有事(すなわち、中国本土と台湾の紛争)に血を流す覚悟を、いつの間にしたのだろうか。
少なくとも私と私の周りの人たちは、誰もそんな覚悟などしていない。
私たちがしなければならない覚悟は、血を流すことではなく、決して戦争で血をながさないことだ。
国や大切な人たちを守るために死ぬ覚悟ではなく、国や大切な人たちのために生きる覚悟だ。
私は、そう思う。
2025年5月23日
学校公開に行ってきた
先日、塾生が通う中学校の学校公開に行ってきた。
塾生の様子ではなく、先生の授業を観るためだ。
中3の英語・国語・社会と中2理科、中1英語を参観した。
結論から言うと、どの授業も、とても退屈した。
例えば中2の理科だ。
詳細は省くが、元素記号が書かれたトランプのようなカードを1枚ずつめくっていき、分子を完成させるものだ。水素分子なら、Hのカードを2枚集める。水ならHのカードを2枚とOのカードを1枚集める。
それで終わり。
その日、塾の授業で訊いてみた。
「あの授業って、何の役に立つの?何を学ぶ授業なの?」
塾生が答えた。
塾生が答えた。
「何を学んだか、ですか?何でしょうね。言われてみると、わかりません。」
「君らは、何を学んでいるかわからずに、あのカードゲームをやっていたの?」
「まぁ、はい。」
「では訊くが、そもそも、原子って何だ?」
「最小の粒子です。」
「原子が最小なんだね?あれ、電子って学ばなかった?」
「あっ。」
「そうだよね。原子は、原子核と電子でできているよね。すると原子は最小の粒子ではない。じゃ、原子がくっついてできる、分子って何?」
「そう言われると、説明できません。」
「君らは、原子も分子も何だかわかっていないんだな?じゃ、また訊くけど、Hが2枚でH2の水素分子ができるんだよね?Hが3枚でH3とか、4枚でH4は作れないの?」
「はい、ダメです。」
「なぜだ?」
「・・・わかりません。」
「原子も原子核も電子も分子も、わからない。Hがどうして2つしかくっつかないのかもわからない。そんなんで、原子分子を勉強したことになるの?」
「・・・」
私に言わせてみれば、業の形を整えただけのようにしか思えない。
もっと言わせてもらえば、ただの「時間つぶし」だ。
あれが「学校教育」とは、少し泣けてくる。
2025年5月 8日
「やばい」に意味はあるか?
そう。最近の若者が頻繁に使う「やばい」「えぐい」あるいは「かわいい」などの言葉は、意味を持っているのだろうか。
どうして、そう思うのか。
一般的な20歳以下の人たちを考える。
すごくおいしいラーメンを食べたとする。その感想で、「やばい」は使わないだろうか。一方で、すごくまずいラーメンを食べた時に「やばい」は使わないだろうか。
野球で、大きく曲がるスライダーの投球を見た時、「えぐっ」と言わないか。あるいは、どこかの国の暴動で多数のケガ人の報道を見た時、「えぐっ」とは言わないだろうか。
つまり、好ましく感じた時も嫌悪感を感じた時も「やばい」「えぐい」が使われる。しかも、ひんぱんに。
いい時も悪い時も使われるのだとすると、それはもはや「感想」とは言えないのではないだろうか。
何を見ても、何を食べても、何をしても。うれしくても悲しくても、楽しくても怒りを感じても。いつでも何でもかんでも「やばい」「えぐい」では、「ただ言葉を発しました」でしかない。
似たように感じる言葉が「かわいい」や「きもい」である。
幼い子供や動物を見た時「かわいい」と感じることはわかる。「きもい=気持ち悪い」も、強い不快感を覚えた時に使うことはわかる。
ところが最近(といっても、もう10年以上も前からだが)では、必ずしも、そのような場面でだけ使われているのではないようだ。
少しでも自分の好みや感覚に合致すれば「かわいい」、少しでも自分の好みや感覚に合わなければ、とたんに「きもい」が使われる。
何かを見た時の感想は、「かわいい」か「ふつう」か「きもい」である。自分の感想を表現するときの言葉が、たった3種類である。極めて単純な分類である。
難しい言葉を使ってほしいわけではない。ただ、「あいまいな表現」「何にでもあてはまる表現」「単純な分類」ばかりでは、日本人としての感性が養われないような気がする。
その結果、誰かとコミュニケーションをとる時でも、相手が一体どう思っているのか、何が言いたいのか、どう返事をすればいいのか、そういったことを理解しえないまま会話が進むような気がする。
それを「コミュニケーション」「会話」と言えるか?
当塾では、使ってはいけない言葉がある。「やばい」「えぐい」も、もちろん使ってはならない言葉である。
2025年4月18日
1学期の過ごし方(中3編)
偉そうなタイトルだが、たいしたことはない。
そう。この時期は、たいしたことをする時期ではないといくことをわかってほしい。
たいしたことをしなくてもいい(=しなければならないことだけをすればいい)代わりに、しなければならないことは必ずしなければならない。
例えば、英語を例にとる。
「たいしたこと」は、単語を覚えること。「しなければならないこと」は、単語を覚える努力をすること。
「たいしたこと」は、文章構成がわかること。「しなければならないこと」は、主語や動詞などの構成要素を考えること。
このように、今の時期は「できなくてもいい」「わからなくてもいい」「覚えていなくてもいい」時期である。
だからといって、そのままの状態でいいわけではない。「今の自分にはできないことがわかった」「わからないことはこれだと気が付いた」「このやり方では覚えられないことがわかった」ということを自覚する時期だということだ。
そうすると、「できるよう、自分の努力のスタイルを探す」「わかるためには何をすればいいかを考える」「自分にあった覚え方を試す」という段階に入る。
口では言えるが、実際は、そんなに簡単ではない。やってもやってもできない。繰り返しても覚えられない、という苦痛の日々が続くからだ。
そして次の段階だ。この「苦痛」が、何かを習得する上で、必ず伴うことに気づく。勉強であろうが、スポーツであろうが、芸術であろうが、技術であろうが、今以上の力を身につけようとすれば、「苦痛」=「努力」しなければならない。
その努力を続けることができれば、「できなくてもいい」→「できる方法を考える」→「努力をする」→「できるようになる」という変化をたどる。
この「努力」の場面は、当塾の場合、夏休み頃だろう。夏までに、自分の「勉強スタイル」を見つけなければならない。1学期とは、そういく時期だ。たいしたことはない。
2025年3月25日
授業の終わりに
(小学生授業の終盤)さて、そろそろ時間が来ました。何か聞いておきたいことはありますか?
「はい、あります。どうして法律ってあるんですか?」
おっ、いい質問だね。
それはね、みんなが安心して暮らすためなんだよ。
「安心してって、どういうことですか?」
例えば、泥棒が許されるとするよ。AさんがBさんのを盗んだら、盗んだAさんは幸せかもしれないね。でも、盗まれたBさんは幸せじゃないよね。だから今度は、BさんがCさんから何かを盗みかもしれない。そうすると、あっちこっちに泥棒がいることになる。これは幸せなことじゃないよね。
また、何をしてもいいんだったら、殴り合いだって、あっちこっちで起きる。
そうならないように、法律をつくって、みんながすこしづつ我慢をして、そのかわり平和な社会で安心して暮らそうってことなんだ。
「なるほど。」
これが、中学3年生の「公民」の授業では、全く逆のことを言うことになる。
表向きでは、「法律は社会秩序を維持するためにある」ことになっている。でも現実はそうとは思えない。
法律は、権力者が国民を管理統制しやすいようにできているとも言える。
例えば、国民全員がマイナンバーカードを作らなければならない。それは、国民への行政サービスが迅速に提供でき、国民が煩わしい手続きから解放されるからだという。
しかし実際には、このマイナンバーカードに保健証や免許証などが一体になり、ナンバーさえわかれば、その人の健康や生活面がわかり、納税状況もわかり、法律違反状況もわかる。
要するに、このマイナンバーカードで、個人情報が何でもわかってしまう。
自分のことを役所に知られたくないとしても、こうなると、何でも知られてしまう。
だから法律などの規則は、国民のためというよりも、政治家や役所のためだとも言える。
法律を作るのは「国会」で、「国会議員」だ。国会議員は選挙で選ばれる。だから君たちは3年後、選挙権を手にしたら、誰に投票するかを、しっかりと考えなければいけないことがわかるね。
さぁ、次は...。
2025年2月 7日
逆転の思考(その2)
この時期から新年度の塾を探している方も多いと思う。そこで今回取り上げる内容がこれだ。
勉強の仕方がわからないから勉強しない。
→勉強しないから、勉強の仕方がわからない。
多くの児童・生徒が口にするのが、このセリフだ。保護者のみなさんも、「勉強しようにも、どうやって勉強したらいいかがわからない」と言われれば、ついつい納得してしまう。むしろ、勉強の仕方がわからない我が子を不憫に思ったりもする。
そこで「だったら、塾に行って、勉強の仕方を教えてもらおう」ということになる。
ところが、考えてみてほしい。誰にでも当てはまる、そして簡単で、あっというまに勉強ができるようになる方法というものがあるだろうか。もしあるなら、なぜ「勉強ができる人とできない人がいる」のだろうか。
結論から言うと、「誰でも勉強ができるようになる効率的な勉強方法」など、ない。それぞれに合った勉強方法は、それぞれが見つけるしかない。そして自分に合った勉強方法は、まずは勉強を始めなければ見つからない。勉強を始めても、ああやってもダメ、こうやってもダメが繰り返される。それでも、「こうしてみればどうだろう」という試みを何度も繰り返す。そうしてついに「あぁ、こうすればいいんだ」と気づく。これがあなたの勉強方法だ。そして、この過程を「努力」と呼ぶ。
数学の例を挙げてみよう。
当塾の数学学習では、自分の「勉強の方法」を探す旅は、「書いて考える」から始まる。頭で考えて書き、書いてまた考える。決して頭だけで考えてはいけない。書きながら、ノートの上で考える。そのノートに書くことは、塾生によって大きく異なる。それは方程式の文章題だろうが、関数だろうが、図形だろうが、あるいは途中計算の筆算だろうが、何から何まで書く。正しかろうが間違っていようが、そんなことは問題ではない。書いて考えることが大事なのである。間違えたら書き直す。書いて考えれば、ミスが減るとともに、「論理的な考え方」が身につく。自分の考え方や進め方が間違っていれば、必ずそこに「論理の破綻」がある。つじつまが合わなくなる。そのことは、「鉛筆が止まる」という形であらわれるから、「あれ、おかしい」とすぐ自分で気づく。間違った時でも、消しゴムで消さない。正しい考え方と間違った考え方の両方を、後で見直すからだ。
とにかく、書いて書いて書きまくる。どの問題でもこれを行う。そうすれば、約束してもいい。必ず「自分の勉強方法」が見つかる。