ひとは、死んだらどうなるのか?
「ひとは、死んだらどうなるのか」「ひとは、何のために生きるのか」。小学校高学年から、遅くても中学生2年生くらいまでには、「生きるということ」「死ぬということ」についての疑問を持つ。
ひとは、死んだらどうなるのか。どうにもならないし、何にもならない。命が消える、ただそれだけだと思う。
「命」とは、何かの形として存在するのではなく、身体に宿る「生きる力」である。「死ぬ」とは「命を失うこと」つまり「生きる力が消えること」である。
命は、ある意味では、「炎」に似ている。
何かに火を点けると、それは熱と光を放つ炎になる。炎は風が吹けば消えるし、そのままにしておいても、いつかは消える。消えた火は、その形を何かに変えたわけではなく、どこか別の場所に移動したわけでもない。ただ消えただけだ。
ひとの死についても、消えた命が別の形に変わったわけでもなければ、どこか別の場所に移動したわけでもない。
点けられた火は何かの折に消えてしまうこともあるが、何もしなくても、ただ燃えているだけだ。
しかし、その光と熱を活かすこともできる。闇の中で不安でいる人や進むべき道に迷っている人に、光は安心を与えてくれ、行き先を照らしてくれる。寂しい人や心が寒くて震えている人に、火は暖かさをくれる。
命と炎が違う点と言えば、炎は燃えるものと空気さえあれば燃え続ける一方、ひとが生き続けるには理由が要る。いわゆる「生きがい」「目標」と言われるものだ。命=生きる力は、ひとの内部から自然に湧き上がってくるものではない。もしそうなら、何の悩みもなく充実して楽しい毎日を送っているはずだ。
生きる理由は、自分自身でつくらなければならない。「探す」のではない。「つくる」のだ。生きがいや目標がどこかにあるのなら、誰でもいつかは見つけることができるだろう。しかしそんなものは誰も用意してくれないし、どこかにあるわけでもない。
生きる理由は、自分でつくるしかない。
「ひとは、何のために生きるのか」これは、誰もが納得できる答えがあることが前提の質問だ。ひとが生きる理由がどこかにあると、なぜわかるのか。
生きる理由がどこにもないなら、自分でつくれ。何でもいい。「明日は、この服を着よう」でもいいし、「今週末は食べ放題に行こう」でもいい。
一生懸命に考えても生きる理由が見つからなければ、生きる理由なんかなくてもいいと思えばいい。火が光や暖かさを与えてくれるように、君の生きる力は、きっと誰かに光と温かさと笑顔をもたらしていると思う。
生きる理由なんかなくても、それだけで十分だ。それだけで、生きる価値がある。
僕は、そう思う。
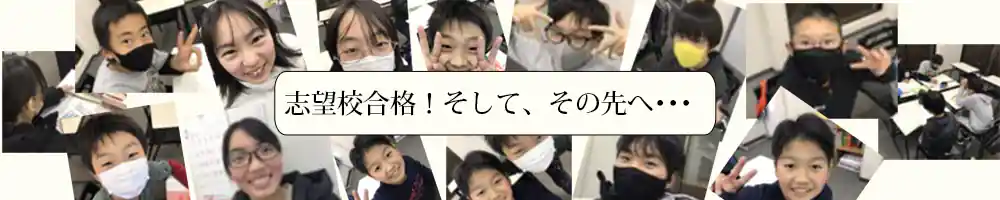

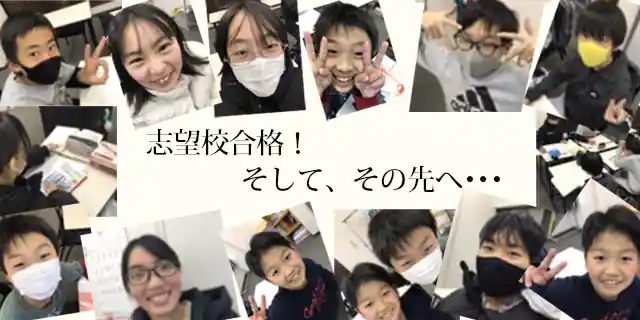






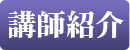
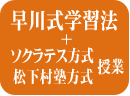
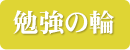


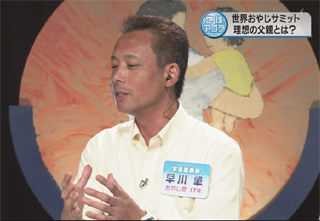


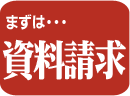
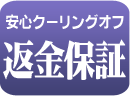

コメントする